葬儀後の手続きの1つに受給資格の制限はありますが遺族年金制度というのがあります。
昔は女性の社会進出が男性に比べて少なかったので、一家の大黒柱であるご主人が亡くなるとその家族の生活は大変になってしまいます。
現在、遺族年金を受給されている方の多くが女性です。
時代が変わり今や女性が社会で活躍する時代になっています。
そのせいか遺族厚生年金の見直しとして男女平等、男女差の解消の1つとして年金の改正が検討されているようです。
遺族基礎年金・遺族厚生年金←クリック!!
男女平等ということですが、実際にはその裏には何かが隠されているのではないでしょうか?
残されたご遺族の助けになるような改正になってもらいたいと思います。


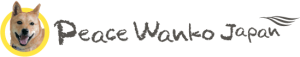








 。
。

